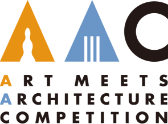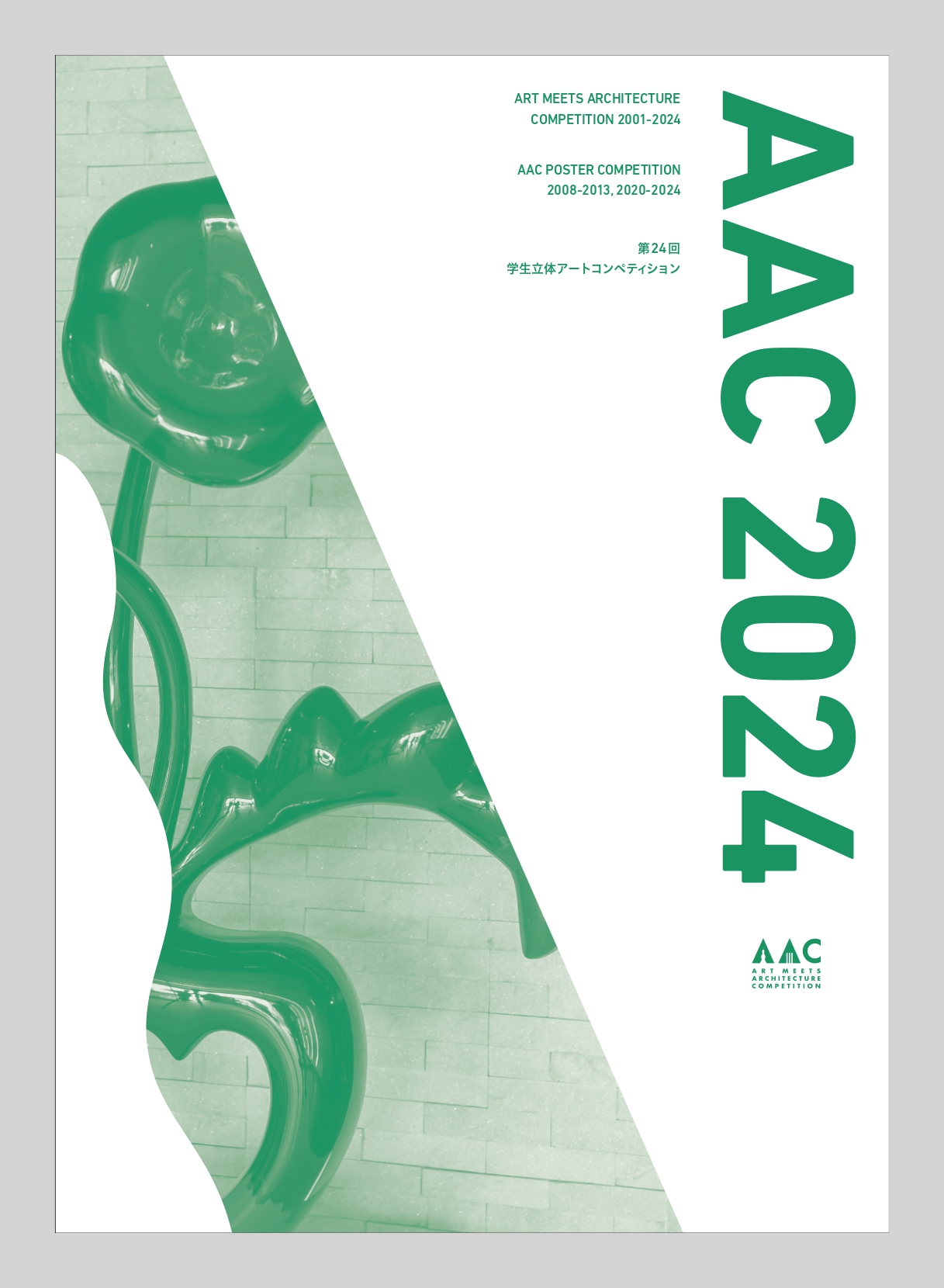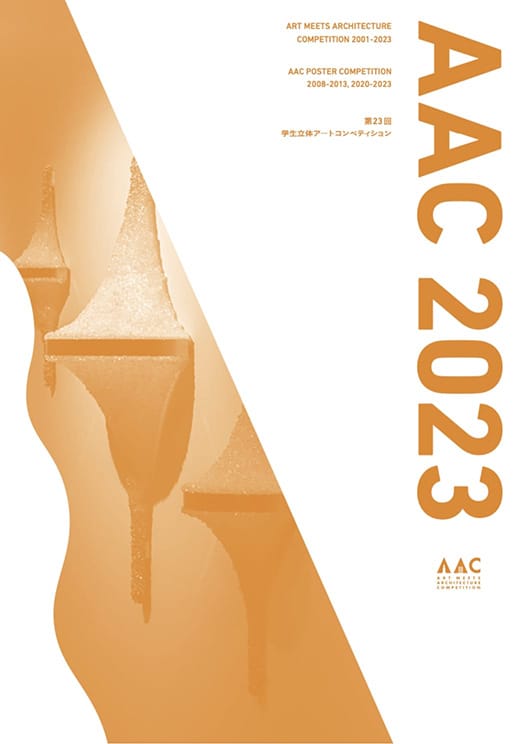Archive
アーカイブ
-
AAC 2024
- 最優秀賞
- 中居瑞菜子|Be yourself
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 三原航大|方舟
大阪芸術大学大学院
遠藤由季子|黎明の途
富山ガラス造形研究所 - 審査員
- 鈴木芳雄 編集者/美術ジャーナリスト
三沢厚彦 彫刻家
藪前知子 東京都現代美術館学芸員
服部信治 主催会社 代表取締役会長兼CEO - 設置場所
- 戸越プロジェクト(東京都品川区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 北田恵一|円柱 want you
武蔵野美術大学 - 審査員
- 宮本武典 キュレーター/東京藝術大学准教授
佐々木俊 グラフィックデザイナー
服部信治 主催会社 代表取締役会長兼CEO
-
AAC 2023
- 最優秀賞
- 洪 詩楽|星群
多摩美術大学4年 - 優秀賞
- 杉森 杏香|日々泡
京都市立芸術大学大学院
五十嵐 俊治|Kasane
東京大学大学院 - 審査員
- 秋元 雄史 東京藝術大学名誉教授/美術評論家
西澤 徹夫 建築家
小山 登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役社長/本現代美術商協会(CADAN) 代表理事
服部 信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- (仮称)西大井プロジェクト(東京都品川区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 松井 寛太|試行錯誤
多摩美術大学 - 審査員
- 上西 祐理 アートディレクター/グラフィックデザイナー
宮本 武典 キュレーター/東京藝術大学准教授
服部 信治 主催会社 代表者
-
AAC 2022
- 最優秀賞
- 平尾祐里菜|千種万花
広島市立大学大学院 - 優秀賞
- 袁方洲|サクラの柱
東京藝術大学大学院
中居瑞菜子|杜の黎明
東京藝術大学大学院 - 審査員
- 保坂健二朗 滋賀県立美術館ディレクター(館長)
岩渕貞哉 「美術手帖」総編集長 大竹利絵子 彫刻家
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- 錦糸町Vプロジェクト(東京都江東区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 鮎川裕之伸|作る
多摩美術大学 - 審査員
- ナカムラクニオ 「6次元」主宰/映像ディレクター
上西祐理 アートディレクター/グラフィックデザイナー
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2021
- 最優秀賞
- 隗楠|Power
of Flower 京都市立芸術大学大学院 - 優秀賞
- 袁方洲|さんすいの間
東京藝術大学大学院
山口聡士|蜃気回層
東京工業大学大学院 - 審査員
- 青木淳 建築家/京都市美術館館長
荒神明香/南川憲二 現代アートチーム 目[mé]
小山登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社
代表取締役社長/日本現代美術商協会(CADAN) 代表理事
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージグランデときわ台アジールコート(東京都 板橋区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 大橋佐和子|get bigger
呉工業高等専門学校 - 審査員
- 古平正義 アートディレクター/デザイナー
ナカムラクニオ 「6次元」主宰/映像ディレクター
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2020
- 最優秀賞
- 勝川夏樹|Microcosm
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- グループ名:hamuhamu ー 早坂雅寿・堀真代 |ひとときひととき
東京都立大学
山﨑稚子|むれやなぎ
文化服装学院 - 審査員
- 片岡真実 森美術館 館長
宮津大輔 アート・コレクター/横浜美術大学 学長
大成哲 彫刻家/第1回AAC優秀賞受賞
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- メイクス新中野アジールコート(東京都 中野区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 藤田理紗子|空間に産む
女子美術大学 - 審査員
- 森井ユカ 立体造形家/雑貨コレクター
古平正義 アートディレクター/デザイナー
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2019
- 最優秀賞
- 白谷琢磨|the city
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 番原耕一郎|Neighbor
広島市立大学大学院
五十嵐亮太|半分の阿吽
東京藝術大学大学院 - 審査員
- 藤森照信 建築家/建築史家/東京都江戸東京博物館館長
橋本麻里 ライター/エディター/公益財団法人永青文庫副館長
小山登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役社長
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- アジールコート台東根岸(東京都 台東区)
-
AAC 2018
- 最優秀賞
- 雷康寧|Be water my friend
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 佐野圭亮|現の秤
東京藝術大学大学院
堀田光彦|精神の美
東京藝術大学大学院 - 審査員
- 馬渕明子 国立西洋美術館館長
ヤノベケンジ 現代芸術作家
内田真由美 アート・コーディネーター
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージファースト両国IIアジールコート(東京都 墨田区)
-
AAC 2017
- 最優秀賞
- 金俊来|Waterfall
京都市立芸術大学大学院 - 優秀賞
- 後藤宙|Heterogen
東京藝術大学大学院
土井彩香|Starting from white
東京藝術大学大学院 - 審査員
- 堀元彰 東京オペラシティアートギャラリーチーフ・キュレーター
三沢厚彦 彫刻家
小山登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役社長
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- AXAS代々木八幡アジールコート(東京都 渋谷区)
-
AAC 2016
- 最優秀賞
- 古川千夏|GEMME
広島市立大学大学院 - 優秀賞
- 中尾俊祐|Corona
和歌山大学
堀田光彦|朝の輝き
東京藝術大学大学院 - 審査員
- 秋元雄史 東京藝術大学大学美術館館長/金沢21世紀美術館館長
望月かおる 月刊『美術手帖』副編集長
内田真由美 アート・コーディネーター
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージファースト蔵前IIアジールコート(東京都 台東区)
-
AAC 2015
- 最優秀賞
- 渡辺志桜里|ひとつのうみ
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 佐藤風太|気配
東京藝術大学
金俊来|日の出
京都市立芸術大学大学院 - 審査員
- 清水敏男 TOSHIO SHIMIZU ART OFFICE代表
鈴木芳雄 編集者/美術ジャーナリスト/愛知県立芸術大学客員教授
小山登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役社長
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージグランデ清澄白河アジールコート(東京都 江東区)
-
AAC 2014
- 最優秀賞
- 井田大介|UNTITLED
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 穴井麻美|見つめる
多摩美術大学大学院
グループ名:進藤・山崎・前原・横田|フォトンの日々
進藤篤 東京藝術大学大学院
山崎明史 日本大学大学院
前原良平 日本大学
横田安紀 日本大学 - 審査員
- 塩田純一 新潟市美術館館長/美術評論家
岩渕貞哉 月刊『美術手帖』編集長
森千花 東京都現代美術館 学芸員
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- グランドコンシェルジュ新御徒町アジールコート(東京都 台東区)
-
AAC 2013
- 最優秀賞
- 村上仁美|eternal moment
愛知県立芸術大学大学院 - 優秀賞
- 大野晴美|Human sign
女子美術大学大学院
安達淳|表出
武蔵野美術大学大学院 - 審査員
- 土屋公雄 彫刻家/愛知県立芸術大学教授
小山登美夫 小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役社長
宮村周子 編集者/ライター
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージグランデ蒲田アジールコート(東京都 大田区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 関谷大志朗|なにをみる。
関西大学大学院 - 審査員
- 高井薫 株式会社サン・アド アートディレクター
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2012
- 最優秀賞
- 帆足枝里子|景
女子美術大学大学院 - 優秀賞
- グループ名:金保/平山 ー 金保洋・平山里紗|結
金沢美術工芸大学
山口恵美|catena
佐賀大学大学院 - 審査員
- 南條史生 森美術館館長
広本伸幸 実践美学者 児島やよい
キュレーター/コーディネーター/ライター
服部信治 主催会社 代表者
設置場所 AXAS上野北(東京都 台東区) - 設置場所
- AXAS上野北(東京都 台東区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 戸塚香里|あたらしい鏡
武蔵野美術大学 - 審査員
- 長嶋りかこ 博報堂 アートディレクター/デザイナー
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2011
- 最優秀賞
- 堀康史|HOPE
多摩美術大学 - 優秀賞
- 帆足枝里子|土塊
女子美術大学大学院
向川千世|時を紡いで
大阪教育大学大学院 - 審査員
- 酒井忠康 世田谷美術館館長/美術評論家
岩渕貞哉 月刊『美術手帖』編集長
内田真由美 アート・コーディネーター
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- ステージファースト両国アジールコート(東京都 墨田区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 藤平奈央子|平面から立体へ
日本大学 - 審査員
- 帆足英里子 株式会社ライトパブリシティ アートディレクター
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2010
- 最優秀賞
- 宮原嵩広|A.S.series「第二の扉」
東京藝術大学大学院 - 優秀賞
- 堀康史|セルメン
多摩美術大学
小野真由|彩
多摩美術大学 - 審査員
- 新見隆 デザイン・美術評論家/キュレーター
植松奎二 芸術家
千葉由美子 ユミコチバアソシエイツ代表
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- AXAS森下sta.(東京都 江東区)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 増川友梨・齋藤菜月|HOUSE
AAC 女子美術大学 - 審査員
- 杉山ユキ 株式会社博報堂 アートディレクター
服部信治 主催会社 代表者
-
AAC 2009
- 最優秀賞
- 八木貴史|天上の虹
武蔵野美術大学大学院 - 優秀賞
- 片井彩霞|うずくまる
九州産業大学大学院
本郷芳哉|立つこと
東京藝術大学 - 審査員
- 小池一子 クリエイティブディレクター
堀元彰 東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーター
白石正美 白石コンテンポラリーアート代表
北澤ひろみ キュレーター
服部信治 主催会社 代表者 - 設置場所
- アジールコート武蔵小杉(神奈川県 川崎市)
- [ポスター部門]
- 最優秀賞
- 村岡あさこ|手に豆が出来る程
多摩美術大学 - 審査員
- えぐちりか アーティスト/アートディレクター
北澤ひろみ キュレーター
服部信治 主催会社 代表者